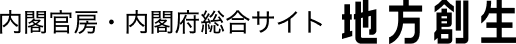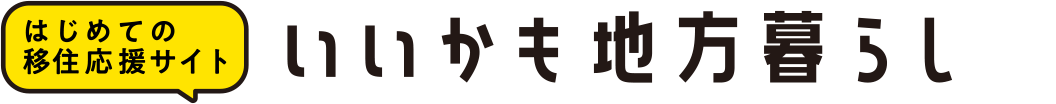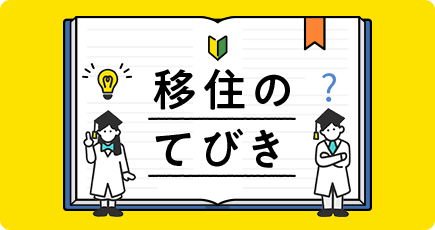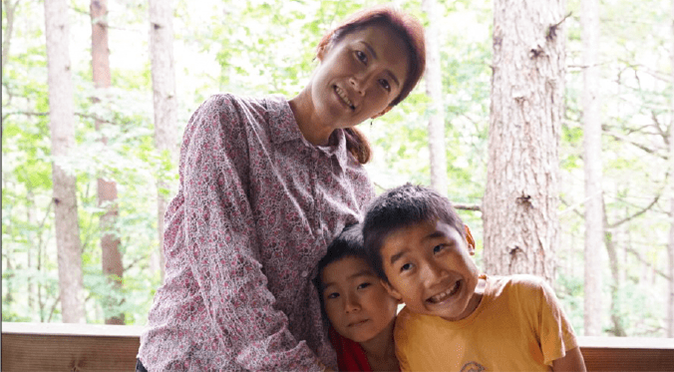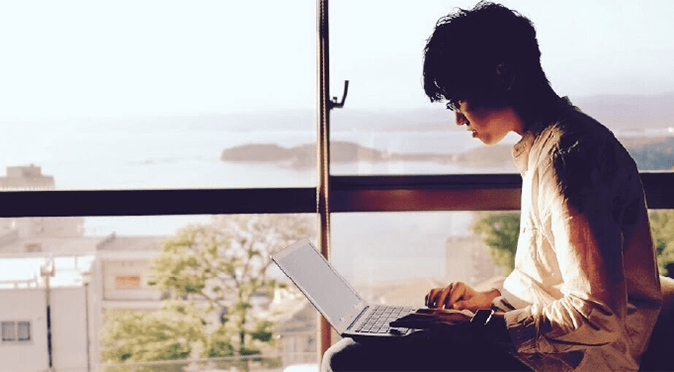静岡の茶工場を引き継ぎ移住。茶の製造、文化を継承したい
水野 嘉彦さん

水野 嘉彦さん
東京都出身。2019年4月に東京都から静岡県静岡市に移住。
- 移住時の年代:20代
- 家族構成:独身
- 移住スタイル:Iターン
- 職業:会社経営
起業の一環で“オクシズ”へ移住を決意
「東京にいるころは地元の人と密接に関わることはなかったのですが、こちらではお茶の業界の人をはじめ、いろいろな地元の人と話す機会があり、人間関係がとても広がりましたね。家を出れば周りに大自然が広がっていて、空気もきれいです。柴犬を飼い始めて、近くを流れる安部川のあたりを一緒に散歩したりして、田舎ならではの自由度の高い生活を楽しんでいます」

2019年4月に、現地の茶工場を引き継ぐため、静岡市の中山間部にあり、近年、奥静岡=オクシズとして人気の大河内地区に移住した。もともとが起業家志望で、起業家を目指す人たちの集まりで知り合った男性と、日本茶の生産から販売までをトータルプロデュースするベンチャー企業を、大学3年時の2018年5月に設立した。その業務の一環として全国のお茶農家を回っているときに、静岡市の関係者から茶工場が廃業の危機にあり、できればその仕事を引き継いでほしいとの依頼を受けた。
「起業を模索する中で、僕自身日本の文化や歴史に興味があり、それらを次の世代に繋いでいける仕事をしたいと思い、日本茶を取り扱う会社の立ち上げに参加しました。会社を大きくしていく上で、第1次産業に参入し、原料の茶葉の生産から携わっていくことがプラスになると判断し、茶工場の仕事を引き継ぐために、同僚と2人で移住しました」
移住を決めたのが2018年11月で、実際に移り住むまでの約6か月間、何度もオクシズに通い、茶工場を視察したり、車で地域を回って現地事情を確認したりした。

「『閑散としているなぁ』というのが最初の印象ですね。でも、もともと静かなところが好きだったので、『こういうところも悪くないな』と思いました。むしろ、新しい仕事を始めるということで、わくわく感の方が大きかったです」
住居は築100年を超える古民家
住まいは静岡市が紹介してくれたいくつかの物件から、築100年を超える古民家に決めた。茶工場までは車で2、3分。同僚もすぐ近くにある同じような古民家に住んでいる。
「実家も一軒家なのですが、やはり古民家だと梁とかがすごくしっかりしていて、雰囲気が全然違いますね。一目見て、『ここに住みたい』と思い即決しました。家賃は月1万円です。静岡市からの移住報奨金は20万円。ほかにも、住宅改修補助制度の限度額いっぱいの100万円を活用して、それで部屋のリノベーションと風呂など水回りの改修を行いました。水回りは結構、お金がかかりましたね。それから、心のゆとりも大事ですね。前もって抱いていたイメージとの乖離は必ずあるので、『そういうこともあるよな』くらいの気持ちの余裕を持っていた方がいいと思います」
第1次産業への参入という当初の目的に沿う形で、農地を保有できる資格を持つ「農地所有適格法人」として、2020年4月に新会社を設立し、その代表を務めている。新会社では、茶畑の管理や茶葉の製造のかたわら、パートナー企業と連携して、オリジナル茶葉の開発などに取り組んでいる。普段は朝8時半ころに茶工場に出勤し、昼ごはんをはさんで午後8時か9時ころまで仕事。3度の食事は自炊で、事業の拡大とともに収入も増え、「生活費は東京ほどではないので、家計にもちょっとずつ余裕が出てきた」という。

物より経験に対してお金を使いたい
「移住してから、あれを買いたいとか、これが欲しいといった物に対するこだわりがなくなり、生活を楽しむため、豊かにするために何が必要かを考えるようになりました。完成品を買うのではなく、例えば味噌なら原料から買って手作りするとか、いろいろ手を加えて変化を起こす作業がとても楽しくて、そうした経験に対してお金を使うことが増えました」

「初めて自分たちで加工した茶葉は、地元の人の評価は今一つだったものの、都市圏で販売すると結構高評価だったことで、茶業界の方向性と消費者が求めているものに多少ずれがあるように感じました。業界の仕組みを変えていかないと大事な物が残っていかないと思いますし、そのためには僕たちのような外からの力が必要だと思っています。ここ大河内地区には地元に根付いた文化があり、お茶だけでなくワサビの栽培でも有名で、昔からわさび漬けの製造が盛んに行われています。お茶の葉の製造と並行して、この地の文化を継承していくことも常に頭に置きながら、両方の活動を続けていきたいと思っています」

(2021年12月24日取材)
RECOMMENDおすすめサイト
この記事をシェアする